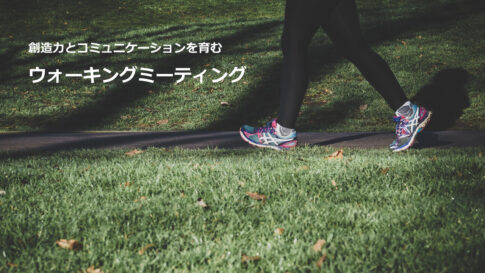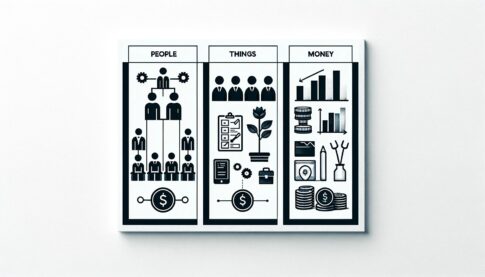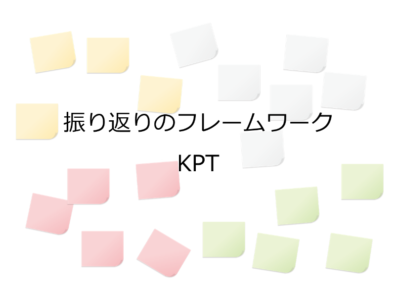企画や製品開発、業務改善などで「新しいアイデアが出てこない」と感じることはよくあります。会議室が静まり返り、誰も意見を出さない――そんな状況を打開するために役立つのがブレインストーミング(ブレスト)とKJ法です。ブレインストーミングは1953年に広告マンのアレックス・オズボーンが提唱した会議手法で、自由な発想を受け入れて新しい解決策を見つけることを目的としています。KJ法は1960年代に文化人類学者の川喜田二郎氏が考案したもので、集めたアイデアをグループ化し、新しい洞察を得るための整理法です。この記事では、これらの手法の基本原則と進め方、最新事情を踏まえたおすすめツールを紹介します。難しい専門用語を避け、誰でも取り入れられるように解説します。
Table of Contents
ブレインストーミングとは何か
ブレインストーミングは、チームで自由に意見を出し合い、批判をしないことを前提にアイデアをたくさん集める手法です。1953年にオズボーンによって紹介されて以来、ビジネスや教育など幅広い分野で使われています。発散思考に重点を置き、従来の枠にとらわれない提案を促すことで、思考の幅を広げることができます。
ブレストの基本原則
プレストの基本原則は下の4つの原則を守りミーティングを行います。
1.他人の意見を批判してはいけない
ブレストの最重要ルールです。批判やダメ出しを行うと発言の意欲を失います。次に発言する人も批判されるのではと思い発言がどんどんなくなります。
2.自由に意見を言い合う
発言に制約をもうけないこと。実現が不可能なことでもOKです。むしろ奇抜さがある方が良いです。
こんなこと言ったら笑われるかもしれないと思うようなジョークのような考えでもよいです。(最後にブラッシュアップすることによって、立派なアイデアになるかもしれません)
アイデア出しの段階では自由であることが大事です。
3.質より量とにかくたくさんの意見を出し合う
大小問わずとにかく意見を出します。アイデアは数で勝負、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」ではないですが、意見をたくさん出す方が次に繋がり、良いアイデアに変わるかもしれません。
4.相手のアイデアに乗っかる
さすがに何個もアイデアを出していると何も思いつかなくなってきます。その場合は他の人が出した意見に乗っかり、自分のアイデアを加えて新しい意見とします。

ブレスト成功のための準備と手順
ブレストを効果的に行うには、事前準備が大切です。次のポイントを押さえましょう。
- テーマを決める – 目的が曖昧だと議論が散漫になります。テーマを明確にし、適宜角度を変えながら進めます。
- メンバー選び – 4〜5人程度の少人数が議論しやすく、多様な視点を得るために部署や立場の異なる人を集めると良いでしょう。
- 時間を区切る – ダラダラ続けないよう時間を決めます。4〜5人なら10分程度が目安です。
- アイデアを発散する – 付箋に書き出し、順番にホワイトボードに貼っていきます。先に述べた四原則を守りながら、とにかく量を出すことが重要です。
ブレインストーミングで使えるツール
オフラインで使えるツール
対面でブレストを行う場合は、ホワイトボードと付箋が基本です。付箋は誰が書いたか色分けし、貼り直しも簡単なのでアイデアの整理に便利です。ホワイトボードがない場合は大きな紙に線を引いて貼っていく方法でも構いません。

オンラインツールの最新動向(2025年)
リモートワークの普及に伴い、オンラインホワイトボードを使ったブレストが増えています。2023年の記事ではGoogle Jamboardが紹介されていましたが、GoogleはJamboardアプリを2024年12月31日で終了し、それ以降は編集不可になると発表しました。Jamboardのデータを保存したい場合は2024年末までに移行が必要で、代替ツールとしてFigJam、Lucidspark、Miroなどを推奨しています。以下では、FigJamとMiroについて簡単に紹介します。
FigJam
- Googleが推奨する代替ツール – Jamboardの終了に合わせ、GoogleはFigJamなどのパートナー製品への移行を案内しています。
- オンラインホワイトボードの概要 – FigJamはAdobe傘下のFigmaが提供するオンラインホワイトボードで、手書きや付箋貼り、図形描画などホワイトボードの操作をデジタルで再現します。デザイナー以外でも扱いやすく、企業や学校など幅広い場面で使われています。
- 主な機能 – 付箋、テキスト、スタンプ、画像、手書き、図形、表、グラフ、投票/アンケート、タイマー、生成AIなど、多彩な機能があります。特に付箋機能では色を変えたり、作成者を確認したりできるので、ブレスト後の整理が容易です。
Miro
Miroは世界で7,000万人以上、日本でも150万人以上が利用するオンラインホワイトボードで、付箋を貼ったり図形を描いたりする自由なコミュニケーションが可能です。各種ツールとの連携により、ミーティング、タスク管理、ファイル共有などの作業を一つのプラットフォームで完結できる点が強みです。DXの推進やチームコミュニケーションの活性化に役立つことから、多くの企業や教育機関に採用されています。
ワンポイント:Lucidsparkという選択肢
Lucid社が提供するLucidsparkは、無限のコラボレーションスペースと仮想付箋を備えたホワイトボードツールで、KJ法やブレストに適しています。ブレストに参加できないメンバーでも後からアイデアを追加でき、タスク化したアイデアをLucidchartへエクスポートすることも可能です。
KJ法でアイデアを整理する
KJ法とは
KJ法は、集めた情報をカードや付箋に書き出し、グループ化して全体像をつかむための整理手法です。1960年代に日本の文化人類学者・川喜田二郎氏が開発したことから、その頭文字を取って「KJ法」と呼ばれます。ブレストで発散させたアイデアを収束させる際に適しており、複雑な問題解決や新しい視点の発見に役立ちます。
使うべき場面
KJ法は、たとえば次のような場面で有効です。
- 複雑な問題を整理したいとき – 大量のデータや意見をカード化して構造化することで、全体像や核心が見えやすくなります。
- 新しい視点やユニークなアイデアを引き出したいとき – 親和図を作成することで自然発生的にアイデアが生まれ、斬新な洞察が得られます。
KJ法の手順
- リーダー(進行役)を決める – セッションの目的を明確にし、参加者の方向性を統一します。
- 問題・テーマを定義する – 解決したい問題やテーマを明確にし、全員と共有します。テーマを目立つ場所に掲示すると方向性がぶれにくくなります。
- 情報・アイデアを集める – ブレインストーミングなどで出てきたアイデアを一枚ずつカードや付箋に記入します。静かに各自のペースで出し合うと幅広い意見が集まります。
- アイデアを整理・グループ化する – 関連するカード同士を自然な形でまとめ、簡潔なラベルを付けます。カテゴリーは後から決めるのがポイントです。
- ラベル付けと再構成 – グループに名前を付け、必要に応じて並び替えながら全体の構造を整えます。
- 全体を俯瞰して次のステップへ – グループ化した結果を一歩引いて確認し、集中すべき課題や次の行動を決めます。
KJ法のメリットと注意点
KJ法には次のような利点があります。
- 多数のアイデアを整理し、優先順位を付けられる。
- チームワークを促進し、客観的な意思決定を支援する。
- ブレストと組み合わせることで創造性とイノベーションを高める。
一方で、時間と労力を要することや、グループダイナミクスによって主観的な影響が出ることもあります。進行役は偏りのない環境を整え、集中しすぎて疲れないよう適宜休憩を挟むとよいでしょう。

ブレインストーミングとKJ法を組み合わせるメリット
ブレインストーミングでアイデアを発散させ、KJ法で収束させると、思考が循環しやすくなります。自由な発想から生まれた多様な意見をグループ化し、関係性を可視化することで、見落としていた問題や革新的な解決策が浮かび上がります。この手法は50年以上前に生まれたものですが、現代のビジネスシーンでも幅広く利用されており、クリエイティブな会議やワークショップにおすすめです
まとめ 次のアイデア会議に活かすために
- ブレインストーミングは批判をしない、自由に発言する、量を重視する、他者のアイデアに乗るという四原則を守り、テーマ・メンバー・時間を適切に設定して行います。
- ブレストの後はKJ法でカードをグループ化し、全体像や関係性を見つけて整理しましょう。
- オンラインホワイトボードのトレンドにも注意が必要です。Jamboardが2024年末で終了するため、代替ツールのFigJamやMiro、Lucidsparkなどを検討しましょう。
これらの手法とツールをうまく組み合わせることで、会議の沈黙を打破し、新しい発想の扉を開くことができます。実際に試して、自分たちのチームに合った方法を見つけてみてください。